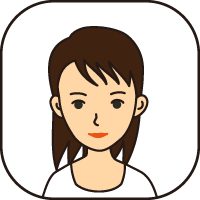Nさん(50代 男性/X染色体連鎖性低リン血症性くる病・骨軟化症)
FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症と診断された患者さんの体験談です。実際の症状や経過には個人差があります。
気になる症状がある方は医師にご相談ください。また必ずしも同じ症状がFGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症と診断されるとは限りません。

Nさん(50代 男性/X染色体連鎖性低リン血症性くる病・骨軟化症)
職業:事務職
現在同居の家族:妻、子ども3人(息子1人、娘2人)
1歳半で「低リン血症性くる病」と診断を受ける
屈伸運動をしなかったことをきっかけに
私の状態に初めて違和感を持ったのは祖母だったそうです。私がハイハイしているときに腕が少し曲がっているように感じていたそうで、立てるようになった子どもが次第に始める屈伸運動をしなかったことで、明らかに何かおかしい…と思ったそうです。当時の母子手帳を確認してみると、立ち始める頃からの身長が平均を下回っていました。それから複数の医療機関を受診し、当時暮らしていた地域で最も規模が大きい病院を受診しても原因は分からず、両親の知人の紹介で受診した東京都内の小児病院でようやく「低リン血症性くる病」と診断されたそうです。私は1歳半でした。
診断がついて以降、月に1回、学校を休んで東京へ行き、小児病院の内科と整形外科の受診を続けていました。また、他の医療機関を受診してみたり、玄米食などいわゆる身体に良いものを試してみたり、矯正靴を履いてみたり、家族は模索してくれました。通院していたので自分は何らかの病気なのだろうとは思いながらも、周囲の友達もみんな普通に接してくれたこともあり、いつかは良くなると思っていました。
ある日、私の身長はもうこのまま伸びないかもしれない、という両親の会話をたまたま耳にしてしまい、自分の病気は一生続くのかもしれない…とショックを受けました。ただ、それも数日だけで、まあそういうものか、とその後は病気を受け入れる気持ちになっていきました。寝るときに足に装具をつけるなど不都合もありましたが、痛みなどはなく、通院を淡々と続けていました。ただ、むし歯になりやすいなど、歯が悪かったことは大変でした。
関連ページ
point
- つかまり立ちを始めた頃に屈伸運動をしなかったことをきっかけに医療機関を受診
- 病気が一生続くのかもしれないことを知り、ショックを受けるも、日常生活に変化はなし
小学校6年生のときにO脚の手術を受ける
交通事故をきっかけに気持ちを切り替える
毎月の小児病院の受診と内服薬による治療を続けていたのですが、O脚がひどくなってきたので、医師の勧めで小学校6年生のときに、膝の外側にボルトを打って矯正する手術を受けました。徒競走が遅かったり、クラブ活動でサッカーができなかったりしたことはありましたが、それ以外は普段の生活に支障がなかったので、治るのであれば治したいから受けてみようか、といった程度で、手術を受けることを深く思い悩んでいたわけではありませんでした。
ところが、手術後に足を伸ばしたり曲げたり、自分で足を上手く動かすことができなくなりました。医師は、「普通に歩けるはずです」と言うものの、なぜか動かない。私は手術前に、膝にボルトなど打ったら足が曲がらなくなるのではないか…と思っていました。この思い込みが強すぎたのかもしれません。自分の意思で足を上手に曲げることができなくなってしまいました。
状況が変わったのは、手術から数か月後に遭った交通事故がきっかけです。両大腿骨が折れてしまう大けがでした。ただ、O脚を矯正する手術を受けて良くなるはずなのに自分のせいで余計に悪くなった、と悩んでいたところだったので、現状が変わるかもしれないとホッとしたと言ってもよいぐらいでした。両大腿骨骨折という大けがですから、入院は3か月にも及びましたし、入院中は寝たきりだったせいか、退院してから歩くときに足裏が痛くなってしまい、足裏の痛みがなくなるまで2~3か月かかるなど、身体的な負担は大きかったです。しかし、交通事故に遭って状況が一変したことがきっかけとなり、O脚の矯正手術後からずっと抱えていた「足を上手に曲げられないのは自分のせいだ」という思い込みはなくなっていました。
point
- 小学校6年生でO脚の手術を受けるも、足を上手く動かせなくなる
- 手術から数か月後に遭った交通事故で気持ちが切り替わる
20歳になった頃から自ずと通院を停止
「子どもの頃だけの病気」という思い込み
O脚を矯正する手術で打ったボルトは、中学生になった頃に外しました。小児病院への通院は続けていましたが、受診は内科だけになり、日常生活で不便を感じるようなことはそれほどありませんでした。ただ、交通事故からの退院後は、それまでは寝るときだけだった装具を昼間も着けるようになり、中学2年生頃まで着けていました。特に不便はなかったのですが、中学生になって制服を着るようになり、学校の椅子と装具が擦れ、制服の生地がすぐ傷んでしまうことが少し気になりました。
成長するに従い、いつまで通院するのだろう、という疑問が浮かび始めました。“小児”病院なのに大人になっても通うのか? と思い始め、医師に質問してみたところ「皆さん、成人する頃になると来なくなります」と言われました。当時は、小児病院ではない別の病院に行くような指示はありませんでしたし、家族からも通院の継続を勧められることもありませんでした。また、私自身も病気に関する知識がなく、あくまでも子どもの病気であり、子どもの頃に薬を飲んで骨を強くすれば問題ない、とその頃は思っていたこともあって、20歳になった頃から自ずと通院しなくなりました。
関連ページ
point
- O脚を矯正する手術で打ったボルトは中学校1年生で外すも、装具は中学2年生頃まで装着を続ける
- 当時は小児病院の医師から転院の指示などはなく、自身の病気に関する知識も乏しかったため、成人してからは自ずと通院をやめてしまった
30代後半で背中に痛みを感じるように
加齢と運動不足による体力の衰えと思っていた
23歳で結婚して、24歳で初めての子どもを授かりました。その間も通院はしていませんし、特に不調もありませんでした。たまに関節の痛みを感じることはありましたが、医療機関を受診しようと思うほどではありませんでした。しかし、30代後半になった頃から、背中に痛みを感じるようになりました。風邪などで咳き込んだときに特にひどかったです。
あまりにも痛いときには近所の整形外科クリニックを受診しましたが、いつもレントゲン撮影と問診で終わっており、血液検査などはしていませんでした。仕事など日常生活に支障はありませんでしたし、まさかこの病気の影響だとは考えもせず、加齢と運動不足で体力が衰えているだけだと思っていました。学生時代のように、運動して体力をつければ自ずと良くなるだろうと思い、専門的な医療機関などを受診せず、治療もしませんでした。
point
- 30代後半から背中に痛みを感じるように
- この病気は子どもの頃だけのものと思い込んでいたので加齢と運動不足の影響だと思っていた
40代後半で大学病院の内分泌内科を受診
身内が調べてくれたことで治療の再開に至る
そのままの状態で10年ぐらい経った40代後半、いよいよ背中の状態がおかしくなりました。背中の筋肉を鍛えるためにやる、腹ばいになって背中を反らせる動きがまったくできなくなったのです。それまでの膝や関節の痛みとは何かが違うと感じたため、家族の勧めもあり、整形外科クリニックを受診しました。ただ、レントゲンを撮ると骨量が少なかったり、関節のあたりにトゲトゲした部分が見られることには気付いてもらえるものの、診察はそこで終わっていました。時には子どもの頃に「低リン血症性くる病」と診断されたことがあるとも伝えましたが、血清リンの測定などの検査はなく、治療を開始することもなかったので、症状も改善しませんでした。
一方、「低リン血症性くる病」は大人になってもう治ったと思い込んでいたので、背中の痛みと何らかの関係がある可能性など思いもせず、自分で調べてみることもありませんでした。ただ、私の妹が医療従事者なのですが、そのような私の様子を見た妹が調べてくれたところ「低リン血症性くる病」は子どもの頃だけのものではないかもしれない、ということを知りました。妹が病院を見つけてくれて、近くの整形外科クリニックの医師の紹介を受けて、現在の主治医がいる大学病院の内分泌内科を受診し、FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症の1つである「X染色体連鎖性低リン血症性くる病・骨軟化症(XLH)」とあらためて診断され、治療を再開しました。
point
- 背中の異常にそれまでの膝や関節の痛みと違うものを感じ、病気を疑い始める
- 40代後半で内分泌内科の専門医によってあらためて「XLH」と診断を受ける
これからのこと
病気でない人と違う経験ができる
私はいま、治療を再開し、普通の暮らしを送ることができています。ただ、授かった子ども3人のうち娘2人ともが私と同じ病気であることが分かり、とても大きなショックを受けました。しかし、私はこれまで、病気を受け入れた上で、「それなら病気でも普通の人と同じように生きられるような人生設計をすればよいだけだ」という思いで生きてきました。これまでを振り返ってみて、病気であってもそれほど悪いものではなかったと思い至り、子どもたちも乗り越えていってくれるのではないかと思っています。
考え方を変えれば、病気であるということは、病気でない人と違う経験ができる、病気である人にしかできない人生を送ることができる、と言うこともできるはずです。身体を動かす仕事は難しいなど、病気のせいでできないこともありますが、自分にできることを活かし、伸ばしていくことによって、病気であっても周囲の役に立つことができる、と前向きに考えていこうと思っています。
関連ページ
この記事の監修ドクター

伊東 伸朗先生
- 東京大学医学部大学院医学系研究科 難治性骨疾患治療開発講座 特任准教授(研究室HP)
- 東京大学医学部附属病院 骨粗鬆症センター 副センター長