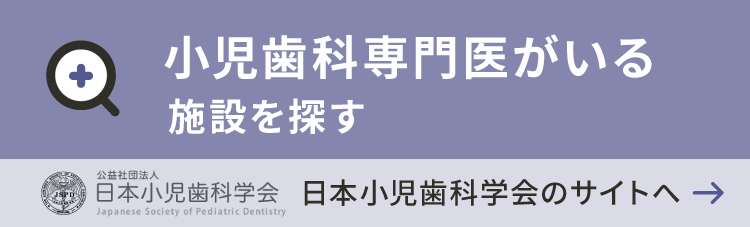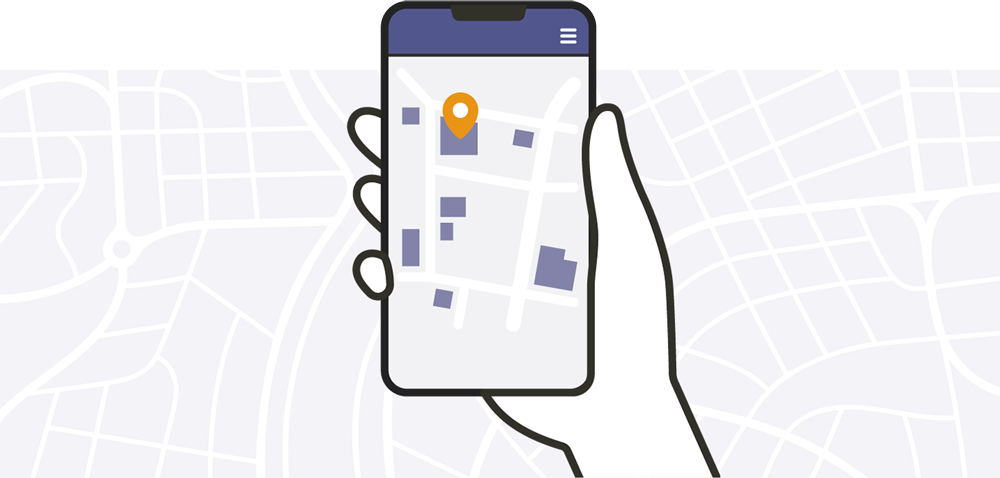XLH Café 開催レポート【2024年10月27日開催】
| 開催日 | 2024年10月27日(日) |
| 開催場所 | オンライン開催+東京・大阪・福岡会場 |
2024年10月27日に開催された、XLHとともに生きる患者さん、ご家族を対象とした市民公開講座「XLH Café」では、大阪、東京、福岡の3会場に加え、オンラインにて患者さんとそのご家族の方々にご参加いただきました。大薗 恵一先生(NPO法人ASridアドバイザリーボード)の開会の言葉に始まり、各先生方からのご講演の後、参加者のみなさんからの質問に先生方からご回答いただく時間が設けられました。ここでは先生方のご講演の一部をご紹介します。
「低リン血症性くる病を知ろう!」
演者: 柏木 博子先生
(独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院 小児科 診療部長)
骨は常に新しく生まれ変わっており、新しい骨が作られるときには、骨を強く、硬くするためのカルシウムとリンによるコーティング(石灰化)が行われます。そのため、カルシウムの吸収を助ける働きを持つビタミンDの作用不足やリンの不足によって石灰化が妨げられると、骨の強さが低下して骨の変形や痛みなどが生じます。このような骨石灰化障害が子どものときに起こるものを「くる病」、大人になってから起こるものを「骨軟化症」と呼びます。リンの不足で起こる「低リン血症性くる病」の中で患者さんが最も多いのが、骨の中にあるFGF23というホルモンが余分に作られる「XLH」です。
受診のきっかけとしては、歩き始めくらいに目立ってくるO脚、X脚が多く、歩き方が気になって受診するケースもあります。小児と成人に共通してみられる症状としては、下肢の変形、低身長、骨の痛み、血清リン値の低下、歯肉膿瘍や歯の合併症などがありますが、成人期では小児期と異なり、変形性の関節症、骨軟化症、偽骨折(骨を横断しない骨折で、激しい運動によらず日常生活の中で起こる。また、治るのに時間がかかる)、こわばり、腱付着部症、難聴などの症状が現れることもあります。これらがすべて現れるとは限りませんが、生涯にわたって幅広い症状がみられることもあるため、成人しても継続して医療機関にかかりながら健康管理をしていくことが大切です。(参考記事:FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症とは?)
小児期医療から成人期医療につなぐ医療のことを移行期医療、トランジションと呼び、小児診療科から成人診療科にどこかの時点で変わるパターン、小児診療科がメインで診察を続けながら必要に応じて成人診療科が関わるパターン、小児診療科が診察を続けるパターンの主に3つがあります。どのパターンをとるかは、病院や施設の体制、患者さんの希望によってさまざまですが、進学、就職、結婚など、ライフステージの変化で見直しが必要になるかもしれません。担当医とよく話し合って医療を途切れないようにすること、ご自身の病気や治療についてよく知って、成人になっても通院、治療を続けることが最も重要です。
「低リン血症性骨軟化症を知ろう!」
演者: 今西 康雄先生
(大阪公立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 准教授)
この病気だということが分からなかったために、小児期に十分な治療が受けられなかった患者さんがいらっしゃいます。そのような患者さんの場合、成人してからも下肢の変形が続いて最終的に偽骨折が起こってしまい、痛みを抱えたまま生活しなくてはならないこともあります。実際XLHの患者さんの骨折歴をみると、多くの方が骨折を経験していますし、骨折の他にも歯肉膿瘍や虫歯などの歯科疾患や、耳鳴りや難聴、高血圧を患う方も多く、総合的に診ていかなければならない疾患です。(参考記事:骨軟化症の症状)
しかし、このようなさまざまな合併症があるにも関わらず、XLH患者さんの生活の満足度を調査してみると、「ふつう」や「満足」という方が3割くらいいらっしゃいます。症状が軽いこともあるかもしれませんが、小さい頃からずっと症状がある状態が続いているので、現在の状態が自分の正常、ということで満足されているのかもしれません。一方で、「非常に不満」、「不満」の方も6割程度いらっしゃいますし、現状不満を感じていない方もしっかりと治療をすれば、身体機能が改善する可能性もありますので、希望を持っていただければと思います。
この疾患は、乳幼児期、小児期から思春期、中年期以降、高齢者と、時期によって身体のさまざまな部位に異なるトラブルが起こりうるため、多職種連携、そして移行期医療、トランジションについて真剣に考える必要があります。小児のときは親と一緒に診察を受けるため、お子さんが自身の病気のことを十分に理解できていないまま成長して、進学や就職をきっかけに親元を離れることもあります。そうすると、何かトラブルが起きたときに適切な治療が十分に受けられず、病気が悪化してしまうことも考えられます。そのため、自分の病気のことをしっかりと理解する、自分で説明ができるようになるなど、自立することが非常に重要です。(参考記事:X染色体連鎖性低リン血症性くる病・骨軟化症(XLH)の通院を大人になっても継続する意義とは)
「X染色体連鎖性低リン血症性くる病・骨軟化症(XLH)治療継続の意義」
演者: 長谷川 行洋先生
(地方独立行政法人 東京都立病院機構
東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科)
XLHの「X」はX染色体に由来しています。人には体質を決めている染色体というものが46本あって、その中でも性別を決めている性染色体がX染色体とY染色体です。XLHはX染色体にのっている遺伝子に原因がある疾患であるために遺伝します。遺伝子に原因があると聞くと、あまり良い気持ちがしないのではないかと思いますが、健常な方もハンディキャップを持っている方も、我々の誰もが2万個以上の遺伝子の中に、働かない遺伝子を持っています。XLHは遺伝子に原因があり、FGF23というホルモンが過剰になって腎臓からリンが漏れ出てしまう病気です。FGF23が病気の根本にあるということは覚えておいていただければと思います。
日々の診察の中で、早く診断されてもご両親や本人の治療に対する理解には時間を要するので、適切な治療を開始するまでに時間がかかって、時に重症化してしまうケースもあります。また、初期治療がうまくいっても身体の成長が終わったことを機に、症状が軽快することがあるので治療を中断してしまい、再び症状が悪化してから再受診となるケースもあります。これらの患者さんの経験からいえることは、小児期に症状があって治療を必要とした方は、おそらく生涯治療が必要だということです。小児期での症状があまりない方をいつまで治療するのかは難しい問題なのですが、少なくともレントゲンで気になるところがある、歩き方が気になる、血液検査をしたらリンが低かった、そのような理由で子どもの頃に診断されている方は、成人になっても治療を止めないで続けてほしい、と思います。(参考記事:FGF23関連低リン血症性くる病と診断された方へ)
一方、この疾患を専門に診ることができる施設はかなり限られています。東京であっても、この疾患を多く診ている施設に限定すると決して多くはありません。そのため、お住まいの地域によっては遠方まで通院せざるを得ないこともありますが、定期的に通院して、治療を続けるということが大切です。
「X染色体連鎖性低リン血症性くる病・骨軟化症(XLH)を知ろう」
演者: 髙士 祐一先生
(福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科学講座 准教授)
XLHの患者さんは2万人に1人と非常に患者数の少ない希少疾患ではありますが、日本だと6,500人、世界だと35万人の患者さんが存在していることになります*。XLHの治療で何よりも大切なのは治療を継続することです。治療し続けることで、下肢の変形や歩行障害を軽減できますし、骨折の予防もできます。また成人期の症状が起きたときに遅れずに治療をすることができます。継続した歯のケアも非常に大切です。XLHは遺伝する可能性がある疾患だからこそ、継続的な治療をすることで次世代が発症した場合に、早期診断・早期治療が可能になります。
希少疾患であるがゆえに情報が少なく、一般の方が正しい情報にたどり着くのは難しいかもしれません。協和キリンで制作しているFGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症の情報サイト「くるこつ広場」では、疾患のことから診断と治療、患者さんの体験談、医療費助成制度についても掲載しています。疾患に関するお悩みや気になる点を看護師、保健師さんに相談することができる「くるこつ電話相談室」もありますので、何か気になることや困ったことがある場合は、治療を受けられている方は我々主治医でも良いですし、そうでない方はこちらにご相談いただくのも一つの解決方法かと思います。受診を迷われている方も近くの病院を案内してもらうことができますので、ご活用いただくのが良いでしょう。
*Endo I, et al. Endocr J 62: 811-816, 2015